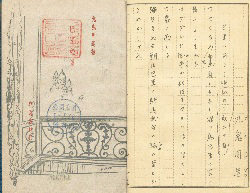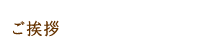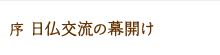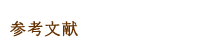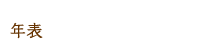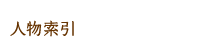![]()
3. 九鬼周造―巴里から江戸へ
哲学者・九鬼周造(1888-1941)は、大正10(1921)年10月から妻を伴ってヨーロッパに留学し、ドイツのハインリヒ・リッケルト(1863-1936)、マルティン・ハイデッガー(1889-1976)、フランスのアンリ・ベルクソン(1859-1941)らに学んだ。昭和4(1929)年1月に帰国するまで、7年余の長期にわたる滞欧であった。1920年代には、戦災で疲弊した欧州に対して日本の経済水準が相対的に高まっており、留学生にとって幸福な時代であった。パリ滞在中、九鬼はフランス語の個人教師として、まだ学生だったジャン・ポール・サルトル(1905-1980)を雇っており、甲南大学九鬼周造文庫に「サルトル氏」と題するノートが残されている。サルトルが九鬼を通じて、ドイツの新思潮であった現象学を知ったという説もある。九鬼は京都帝国大学に迎えられることとなり、帰国の途上、駐米大使となっていたポール・クローデルをワシントンに訪ねている。帰国後は、フランス哲学を講じた。
九鬼周造『巴里心景』甲鳥書林,1942【911.56-Ku779p】
大正14(1925)年から昭和2(1927)年にかけて、九鬼は変名(S・K、小森鹿三)で多くの詩歌を与謝野鉄幹(1873-1935)が主宰する第二次『明星』に書き送った。京都帝国大学教授時代、祇園から人力車で講義に通ったと伝わるが、パリ時代にも粋人ぶりを発揮したらしく、「くしけづるブロンドの髪灯に映えて明し幸ある閨の空気よ」、「アカシヤの木を蔭とする春の夜のうす月を踏むわれと人妻」など艶っぽい歌も見られる。これらの詩歌は、九鬼の死後、親友の哲学者・天野貞祐(1884-1980)によって『巴里心景』として編集され、同じく親友の美術史家・児島喜久雄(1887-1950)の挿画を付して刊行された。天野は九鬼を評して、「この鋭利厳密な分析家は不思議にも同時に勝れた芸術的魂であった」と述べている。なお、九鬼は後年の論文「日本詩の押韻」において、附録の作例にパリ時代の自作詩を取り上げている。
九鬼周造『「いき」の構造』岩波書店,昭和5(1930)【609-110】
ハイデッガーに学んだ解釈学的方法を用いて、日本人の精神構造を解明した労作として名高い。日本哲学の代表的作品として仏訳もされている。「いき」という日本固有の精神的態度を、江戸文化のうちに分析した本書は、パリ滞在中の草稿「「いき」の本質」が下敷きとなっている。帰国の船上で書いた一文に「私は満七年間欧羅巴に住んで見て始めて日本の文化の美しさが明らかに見えて来た」とあり、西洋経験が九鬼を江戸へと導いたと言える。
九鬼は「いき」を、「垢抜して(諦)、張のある(意気地)、色っぽさ(媚態)」と定義し、自然や芸術のうちにいかに表現されるかを分析する。『巴里心景』で母への思慕とともに歌われた白茶色(母うへのめでたまひつる白茶いろ流行と聞くも憎からぬかな)を、いきの代表的な色彩に挙げている。九鬼の母・波津子(1860-1931)は、周造を妊娠中に岡倉天心(1862-1913)と不倫関係に陥った。心を病んで精神病院に収容された母を、九鬼は生涯慕い続けた。
永井荷風『江戸芸術論』春陽堂,大正9(1920)【391-67】
さて、九鬼以前にも、フランスを通って江戸にたどり着いた人物がいる。永井荷風(1879-1959)は、九鬼の渡仏の15年ほど前、明治40(1907)年から翌年にかけて、横浜正金銀行リヨン支店員としてフランスに滞在し、帰国後『ふらんす物語』を発表して文壇に新風を吹き込んだ。同44(1911)年、大逆事件の囚人たちを乗せた馬車を目撃し、ドレフュス事件を糾弾して亡命を余儀なくされたエミール・ゾラ(1840-1902)の勇気をもたぬことを恥じた。以後、自身を「文学者」ではなく、「専制時代」の「虫けら同然なる町人」であった江戸の「戯作者」の伝統に連なる者と規定した。江戸の名残を尋ね歩き、浮世絵を蒐集するなど、江戸趣味に傾斜し、大正9(1920)年に浮世絵を論じた本書を発表している。フランスから帰国後、失われゆく江戸への愛惜の念から浮世絵の世界に過去を夢見るようになったと述べ、ゴンクールらの浮世絵研究も踏まえて、春信、歌麿、北斎、広重らの芸術を論じている。