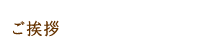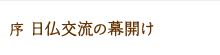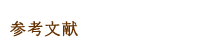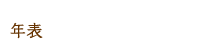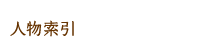![]()
5. 加藤周一―第二の出発
戦後日本を代表する知識人の1人である加藤周一(1919-2008)は、戦時下の東京帝国大学医学部に学ぶ傍ら、仏文学研究室に出入りし、『NRF』【Z55-A228】誌等に載ったフランス現代文学に読み耽った。戦時の狂乱に批判的距離をとる渡辺一夫(1901-1975)助教授のユマニスム研究によって、精神の正常を保つことができたという。戦後、中村真一郎(1918-1997)、福永武彦(1918-1979)と共に、軍国主義を生んだ日本文化の特質を批判する『1946文学的考察』【904-Ka666s】を発表、戦時下の読書を下敷きに活発な評論活動を開始した。その後、昭和26(1951)年から3年間、フランス政府給費留学生としてパリで血液学を学んだ。加藤自身が「西洋見物」と呼んだこの留学は、加藤に日本を再発見させることとなる。帰国後の加藤は、大きな反響を生んだ雑種文化論を皮切りに、文学、芸術、思想の各方面にわたる日本文化論を発表してゆく。加藤の著作は、多くの言語に翻訳され、日本を紹介する手引きとなっている。

加藤周一『羊の歌』岩波書店,1968【910.28-Ka666h】
生い立ちから安保改定の頃までの加藤の自伝。「羊の歳に生まれた、平均に近い日本人」の自己形成を描くとしている。叙述には、ジャン・ポール・サルトルの自伝『言葉』の影響が指摘される。本書で加藤は、フランス留学について、「一九四五年の秋に、戦後日本の社会へ向って出発した私は、五一年の秋に、西洋見物に出かけた。これが私の生涯における第二の出発になった」と述べている。留学中に出会った忘れ難い人びと、西洋文化を通して見た日本、そして人生の針路の選択。3年ぶりに帰国した際、関門海峡から見た日本は、ある確信を与えるものであった。「北九州の海岸や神戸の港に似た風景は、アジアのどこにもない。外国人が外国人のためにつくった設備ではなく、その土地の人間が自らの用に供するためにつくった設備は、(中略)マルセイユ以後日本においてはじめてあらわれる。」 このアジアにおける日本の特殊性の認識が、以後の加藤の仕事の出発点となった。

加藤周一『雑種文化』大日本雄弁会講談社,1956【914.6-Ka666z】
アジアの中にありながら、アジアともヨーロッパとも異なる日本文化のあり方を、加藤は「雑種文化」と表現した。しかし、この「雑種性」について、加藤はマイナスに評価したわけではない。「英佛の文化は純粹種であり、それはそれとして結構である。日本の文化は雑種であり、それはそれとしてまた結構である。」(「日本文化の雑種性」) 日本文化の所与の特性として、外来思想を独自に消化してゆくあり方を積極的に評価し、そこに「希望」を見出そうとしたのである。外来思想を排し土着的なものに純化しようとする傾向も、土着的なものを否定し外来思想一辺倒となる傾向も、ともに日本においては不可能であるとして退けられる。加藤は、市民社会の伝統をもたない日本において大衆の間に民主主義が定着してきたことを、日本文化の雑種性の現れと考え、戦後社会を積極的に擁護しようとする。本書には、加藤が1950年代に展開した一連の雑種文化論を収める。

森有正『バビロンの流れのほとりにて』大日本雄弁会講談社,1957【914.6-M758b】
加藤の留学の前年、戦後初のフランス政府給費留学生として渡仏したのが、哲学者・森有正(1911-1976)であった。加藤とは戦時下の仏文学研究室で親交があり、加藤のパリ到着時には、空港に出迎えている。3年間の留学期間を終えて帰国した加藤と異なり、森はフランスに永住することを選んだ。「ヨーロッパ文明は到底外側から真似のできるような、また単なる観賞によって学べるような、浅い簡単なものではない。僕は僕自身の道を行きつくすところまで行くほかはないのだ」と本書で述べている。国立東洋語学校、パリ大学で教鞭をとり、パリ日本館の館長も務めた。本書以降、日本人と西洋文明の接触を主題とした一連のエッセーを発表し、日本の知識人に大きな影響を与えた。加藤は小説『運命』において、フランスに留まる芸術家と帰国する評論家との、西洋文明の把握をめぐる対話を描いているが、森や滞仏中に親交のあった彫刻家・高田博厚(1900-1987)がモデルと言われる。
日高六郎 [ほか]『サルトルとの対話 2版』人文書院,1980【HD131-E2】
加藤は、日本におけるサルトル紹介者の一人であった。サルトルは九鬼周造の個人教師を務めた後、アグレガシオン(教授資格試験)に合格した1929年頃、東洋文化に惹かれ関西日仏学館の教師に応募している。この時は残念ながら着任に至らなかったが、戦後の昭和41(1966)年に慶應義塾大学と人文書院の招きでシモーヌ・ド・ボーヴォワール(1908-1986)とともに来日している。戦後の世界に絶大な影響を与えた知の巨人の来日に、日本国内は歓迎に沸いた。約1か月間の滞在中、仏文学者の朝吹登水子(1917-2005)の案内で2人は、東京、京都、奈良、大阪、九州、広島などを旅し、各地で講演や知識人との交流をもっている。本書には、加藤、戦後いち早くサルトルを紹介した仏文学者・白井浩司(1917-2004)との鼎談「西欧と日本」等3つの対話を収める。NHKテレビで放映されたこの鼎談でサルトルと加藤は、日本とフランスの間に差異よりも共通性を見る立場で一致している。

ロラン・バルト(宗左近訳)『表徴の帝国』新潮社,1974【GB648-16】
サルトル以後、日本において大きな影響力をもったフランス思想は、構造主義であった。その代表的論者の一人である評論家ロラン・バルト(1915-1980)は、昭和41(1966)年以降、当時東京日仏学院院長を務めていた哲学者モーリス・パンゲ(1929-1991)の招きで3回来日している。その時の印象を元に、記号論的アプローチで日本文化を論じたのが本書である。バルトにとって、記号が意味で満たされた西欧文化に対して、日本は意味が不在の「記号の国(表徴の帝国)」であると位置づけられている。ジャポニストやクローデル、サルトルらが日本文化の意味を探ろうとしたのに対し、バルトは記号の記号としての機能、記号の意味作用を考え、感じ、楽しんだ。記号やテクストの緻密な分析から出発したバルトにとって、テクストの快楽に身をゆだねる後期の思考への転換点となった作品であり、批判の射程は、意味が自然化・絶対化した西欧的認識の抑圧性へと向けられていた。

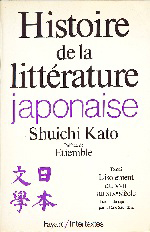
加藤周一『日本文学史序説』筑摩書房,1975【KG12-67】
加藤の後期の仕事は、それまで書き継いできた日本文化論の集大成であった。文学、芸術、思想の各分野について、『日本文学史序説』、『日本 その心とかたち』【K81-H40】、『日本文化における時間と空間』【EC211-H204】がある。これらは各国語に翻訳され、日本文化研究の基本書として広く読まれている。『日本文学史序説』は、昭和48(1973)年1月から同54(1979)年10月まで『朝日ジャーナル』に連載され、後に一書にまとめられた。本書において加藤は、「文学」の概念を拡張し、思想的・宗教的な著作や農民一揆の檄文等も対象に取り上げている。また、近代化を断絶の面からではなく継続の面からとらえ、全体を通じて、日本の土着的な世界観が外来思想の挑戦を受けていかに変容してきたかという観点を叙述の中心に据えている。歴史意識の「古層」を論じた、丸山眞男(1914-1996)の問題意識にも通じる。フランス語版は、1985年から翌年にかけて3分冊で刊行され、好意的に受け入れられた。