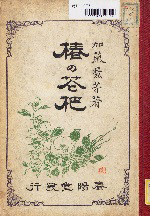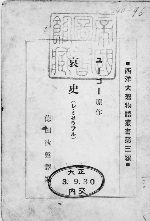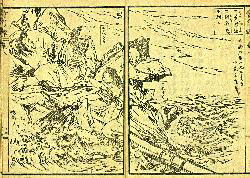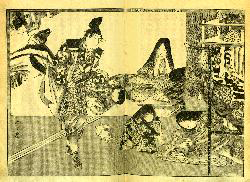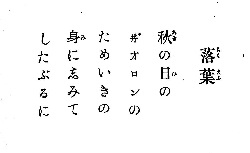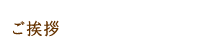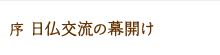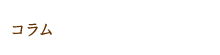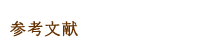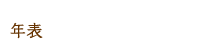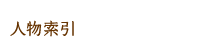![]()
第1章 文学
2. 翻訳されたフランス文学
最初に原典から邦訳されたフランス文学作品は、明治11(1878)年に川島忠之助(1853-1938)が翻訳したジュール・ヴェルヌ(1828-1905)の『八十日間世界一周』である。その後、デュマ父子(父1802-1870、子1824-1895)、ヴィクトール・ユゴー(1802-1885)らの大衆小説や、エミール・ゾラ(1840-1902)、ギ・ド・モーパッサン(1850-1893)らの自然主義文学を始めとする多くの作品が、原典や英訳から次々と訳され、広く受容されていった。一方でその訳文は、時に大幅な省略や登場人物の日本名への置き換え、果ては舞台を日本とするなど、翻案というべき大胆な翻訳(豪傑訳)も多くみられる。当時なじみの薄かった異国の物語を、原作の趣を損なうことなく読者に伝えるために、翻訳者たちが試行錯誤を重ねた様子がうかがえる。
翻訳のはじまり
シェル・ウエルヌ(川島忠之助訳)『八十日間世界一周』川島忠之助,明13(1880)【26-212】
ジュール・ヴェルヌの『Le tour du monde en quatre-vingts jours』の初訳であり、日本で最初にフランス語原典から翻訳された文学作品である。翻訳者の川島忠之助は、横須賀造船所で学んだフランス語を生かして富岡製糸場等の通訳を務め、後に銀行家として活躍した。川島は、蚕糸売り込み使節の通訳として欧米出張した際に英訳版を購求し、これを参考にしつつ、日本ですでに入手していたフランス語原典の翻訳に着手した。帰国後、慶応義塾出版部から前篇を自費出版したが、これは原著の刊行からわずか5年後のことである。前篇が好評であったため、後篇は同出版部が費用をもって出版されている。主人公フォッグが訪れる各地の描写から、読者は世界の多様性を知り、優れた技術や資本、軍事力を持つ国が優勢となるという時代の価値観を受け入れた。本書以降も、ヴェルヌ作品は数多く訳されることとなった。
デュマ父子
関直彦訳『西洋復讐奇談 前編』 金港堂,明20(1887)【23-31】
アレクサンドル・デュマ(父)の代表作『Le Comte de Monte-Cristo(モンテ・クリスト伯)』の初訳。訳者の関直彦(1857-1934)は、当時東京日日新聞記者であり、後に弁護士や政治家として活躍した。原著は、無実の罪を着せられた主人公エドモン・ダンテスが、脱獄後に財宝を手にしてモンテ・クリスト伯と名乗り復讐を果たすまでを描く、全117章からなる大著であるが、本訳書はダンテスが収監された後の第13章部分で終わっている。後編の存在を示唆して結ばれているが、続きは刊行されなかったようである。デュマ(父)の作品は、他にも『Les Trois Mousquetaires(三銃士)』など数多く翻訳されている。
醒々居士 稿,天香逸史 閲『新編黄昏日記』駸々堂,明18(1885)【特41-991】
アレクサンドル・デュマ(子)の初期の長編小説『La Dame aux camélias(椿姫)』(1848)の翻訳で、翻訳者は新聞記者・文学者の小宮山桂介(醒々居士・天香、1855-1930)である。原著は、椿の花を愛して「椿姫」とあだ名される高級娼婦マルグリットが、純朴な青年アルマンと出会い真実の愛に目覚めるが、別離を強いられ肺病で不幸な最期を迎える物語である。本訳書は、序文に「換骨奪体以て我国の人情を写せし」とあるように、マルグリットを「はる」、アルマンを「水瀬清之丞」と改め、舞台を日本に移した翻案となっている。挿絵に描かれた情景も日本風である。
亜歴山戌馬男(アレキサンダー・デュマ)(加藤紫芳訳)『椿の花把』春陽堂,明22(1889)【特11-275】
『La Dame aux camélias(椿姫)』の翻訳で、雑誌『小説萃錦』に掲載後、単行本として刊行された作品である。翻訳者の加藤紫芳(1856-1923)は読売新聞記者であり、他にも同紙にデュマ(父)の『三銃士』の初訳「三人銃卒」を連載している。本訳書では、マルグリットに「馬耳牙理」、アルマンには「阿耳曼」の字を当てているが、舞台はフランスである。いつも椿の花を身に付けているマルグリットの愛称を「椿娘」と訳しており、「椿姫」の称が定着するのは明治36(1903)年刊行の長田秋濤(1871-1915)訳『椿姫』【新別つ-2】を待たなければならない。多くの翻訳がある本作は、デュマ(子)の作品の中で、日本に広く受け入れられた唯一の作品である。
エミール・ゾラと自然主義文学
[エミール・ゾラ](永井荷風訳)『女優ナナ』新声社,明36(1903)【78-42】
永井荷風による、エミール・ゾラの長編小説『Nana』の抄訳と短編小説『L’Inondation』の翻訳、評論「エミールゾラと其の小説」を収録した作品集で、十九世紀文学叢書 第1編として刊行された。日本画家・平福百穂(1877-1933)の装画には、ナナを思わせる女性像が描かれている。『女優ナナ』は、舞台女優から高級娼婦となり、その肉体的魅力で上流階級の男たちを破滅させながら、自らも若くしてこの世を去るナナの人生を赤裸に描いた作品であり、ゾラはフランス自然主義文学の代表作家と目される。この時期の荷風は、ゾラの影響の色濃い作品を次々と発表し、小説家としての地歩を築いた。ゾラの方法論は、小杉天外(1865-1952)や田山花袋(1872-1930)にも影響を与え、日本における自然主義文学の成立に一役買った。
『レ・ミゼラブル』の翻訳
ユゴー(黒岩涙香訳)『噫無情』扶桑堂,明39(1906)【26-371】
『萬朝報』【新-515】を創刊した黒岩涙香(1862-1920)による、ヴィクトール・ユゴーの大作『Les Misérables(レ・ミゼラブル)』の翻訳である。新聞購読者を増やすために魅力ある連載を必要とした涙香は、明治35年(1902)年10月から翌年8月にかけて同作品を掲載し、同39(1906)年に前後篇に分けて刊行した。翻訳の正確性よりも読みやすさを重視した涙香の翻訳は、原作の本筋を保持しながらも、日本人の嗜好にあわせて細部の構成や表現に大胆な改変を加えた翻案であり、「涙香物」と称されて当時の読者に幅広く受け入れられた。1切れのパンを盗んだ罪で19年間投獄されたジャン・バルジャンが、出獄後に改心し波瀾の生涯を終えるまでの物語で、見事な意訳である邦題『噫無情』は、同じく涙香による『巌窟王』(モンテ・クリスト伯)とともに、後の翻訳にも大きな影響を与えた。
徳田秋声 訳編『哀史(レ・ミゼラブル)』 新潮社,大正3(1914)【340-46-(3)】
西洋大著物語叢書 第3編として新潮社から刊行された、小説家・徳田秋声(1871-1943)による『レ・ミゼラブル』の翻訳である。巻頭に記された同叢書の趣旨に「大作を此の掌大の冊子に短縮し、其精髄とも云ふべき部分を簡潔なる物語風の筆によって連綴し、梗概を語ると共に原作の感味を髣髴せしめようとする」とあるように、抄訳シリーズとなっている。本作は、大正7(1918)年に『哀史物語』【31-740】と改題し再刊されている。『レ・ミゼラブル』は、明治20(1887)年の初訳から現在に至るまで人気が絶えることなく、多くの翻訳書が刊行されている。
ピエール・ロチの来日
ピエール・ロチー(飯田旗郎訳)『陸眼八目』春陽堂,明28(1895)【45-277
】
ピエール・ロチ(本名ジュリアン・ヴィヨー、1850-1923)は、海軍兵学校を出て退役までの数十年間、海軍士官として世界各地を回り、その体験を元に多くの作品を著した。原著『Japoneries d'automne(秋の日本)』は、ロチが明治18(1885)年秋に日本に滞在した際の体験をまとめたエッセー集である。本書は、原著から数編を飯田旗軒(1866-1938)が翻訳したもので、同25(1892)年に『婦女雑誌』【雑51-61 】に連載された「江戸の舞踏会」に手を入れ、他の数編と合わせて刊行された。『陸眼八目』のタイトルは、外国人であるロチの視点をなぞらえたもので、訳者・旗軒の見解も交えたかなり自由な訳文となっている。同18(1885)年11月に鹿鳴館で開催された、天長節の舞踏会の体験を描いた「江戸の舞踏会」は、文明開化の一面を克明に伝える貴重な記録である。芥川龍之介(1892-1927)は、短編「舞踏会」にロチを登場させている。
[Pierre Loti](筒井準編)『お菊夫人』誠進堂書店,明35(1902)【139-198(洋)】
ロチの『Madame Chrysanthème(お菊さん)』の初訳である。「お菊」は、ロチが初来日した明治18(1885)年夏に長崎で同棲した日本人の娘おかねがモデルである。日記形式の本作では、あくまでロチの視点で見た日本やお菊の姿が描かれる。ジャポニスムの流行に乗り、フランス本国でベストセラーとなる一方、西洋文明の優位性を疑わなかったロチによる描写は時に辛辣であり、日本への偏見の所産との批判も受けた。
本書は、英語学習者のための読本であり、註釈付きの英文とその和訳を収める。内容はかなり省略されており、日本に対する否定的な表現は見られない。
児童文学
フェネロン(宮島春松訳)『哲烈禍福譚』太盛堂,明治12-13(1879-1880)【特40-617】
聖職者フランソワ・フェヌロン(1651-1715)の『Les Aventures de Télémaque(テレマックの冒険)』の初訳であり、日本語に翻訳されたフランス文学作品の最初期の例の1つである。翻訳者は、官吏としてフランス兵書などの翻訳に携わった宮島春松(1848-1904)で、刊行は全体の3分の1弱にあたる8巻までで終了している。ルイ14世(1638-1715)の孫ブルゴーニュ公(1682-1712)の教材として書かれ、ホメロスの『オデュッセイア』を下敷きに、主人公テレマック(テレマコス)が父ユリース(オデュッセウス)の友人マントール(メントル)に扮した女神ミネルヴ(ミネルウァ、アテナ)とともに数々の冒険を繰り広げながら、理想の君主について学ぶ物語となっている。本訳書では、テレマックを「哲烈」、ユリースを「雄竜士」、マントールを「万執」などと表記し、挿絵にみられる風景表現は日本風である。
ボウマン夫人ほか(井上寛一 訳述,矢野竜渓 補)『西洋仙郷奇談』東陽堂,明29(1896)【68-403】
詩人・童話作家シャルル・ペロー(1628-1703)の『Histoires ou contes du temps passé avec des moralités(過ぎし昔の物語ならびに教訓)』を中心に、ヴィルヌーヴ夫人(1695頃-1755)やボーモン夫人(1711-1780)らフランス人作家の作品を集めた翻訳童話集である。ペロー童話集からは、初訳である「碧髭」、「睡美人(眠れる森の美女)」、「猫君(長靴を履いた猫)」の3作品のほか、「燻娘(シンデレラ)」等が収録されている。山本昇雲(1870-1965)による日本風の挿絵が、異国の物語に和洋折衷の独特な印象をもたらしている。「睡美人」の一場面では、城を訪れた「公達」が美しい寝床の上で眠る姫を目にする様子が描かれるが、装束や調度は日本風である。
ジュウールス・ヴェルヌ(森田思軒訳)『十五少年』博文館,明29(1896)【74-24】
無人島に流れ着いた15人の少年たちの2年間にわたる冒険生活を描いた、ジュール・ヴェルヌの小説『Deux ans de vacances(2年間の休暇)』の初訳で、明治29(1896)年に『少年世界』【Z32-B239】に連載され、単行本化された作品である。翻訳者の森田思軒(1861-1897)は郵便報知新聞記者で、明治19(1886)年に欧米巡航から帰国した後、同紙の娯楽小説欄や雑誌に次々と翻訳小説を発表し人気を博した。本書はその代表作の1つで英訳版からの重訳である。「翻訳王」と称された思軒は、周密文体と言われる漢文調のリズムを持った独特の文体を完成させる一方、原文の趣旨にできる限り忠実な翻訳を目指し、大胆な改変や翻案が横行していた当時の翻訳文学に一石を投じた。
エクトル・マロー(菊池幽芳訳)『家なき児』春陽堂,明45(1912)【329-128】
小説家・大阪毎日新聞記者の菊池幽芳(1870-1947)による、エクトール・マロ(1830-1907)の『Sans famille』の翻訳である。幽芳が同紙に連載し好評を博した、健全な家庭向け小説シリーズの1つとして発表された。逐語訳ではないが、原作の内容をほぼ忠実に再現している。これ以降、本作は『家なき児(子)』の題名で日本に定着した。育ての母であるバルブラン母さんのもとで孤児と知らずに育った少年レミが、旅芸人の老人とともに各地を放浪し、老人の死後も様々な苦難を乗り越え、実の母親に再会するという物語であり、レミの成長とともにレミが旅したフランス各地の様子も描かれる。本訳書では主人公レミが「民」、バルブラン母さんが「直」と、登場人物の名が日本風に改められている。

サン・テグジュペリ(内藤濯訳)『星の王子さま』岩波書店,1953【児953.8-Sa22】
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ(1900-1944)の『Le Petit Prince(小さな王子)』(1943)の初訳である。サン=テグジュペリは民間航空や郵便輸送のパイロットとして活躍する一方、時に危険を伴う自らの体験を元に数々の作品を執筆し高く評価された。第二次世界大戦中の1944年7月、連合軍偵察飛行隊の一員として南仏方面に任務に出たまま消息を絶った。
サハラ砂漠に不時着したパイロットの「ぼく」と、ある星からやってきた「王子さま」との心の交流を、寓意を交えた詩的な文章で描く本作は、1943年にニューヨークで英語版とフランス語版が出版され、作者の死後ベストセラーとなった。130以上の国・地域の言語に翻訳されている。日本では、仏文学者・内藤濯(1883-1977)の翻訳で昭和28(1953)年に刊行され、『星の王子さま』の邦題で現在まで多くの読者に愛されている。なお、作品中に描かれた素朴な挿絵の数々は、原作者自身の手によるものである。
フランス詩の翻訳
上田敏訳『海潮音』本郷書院,明38(1905)【98-192】
英文学者・詩人の上田敏(1874-1916)による訳詩集である。近代を中心にヨーロッパの詩人29人による57編の作品が収録され、うち14人がフランスの詩人である。従来の新体詩に新たな詩形や韻律による新風を吹き込むとともに、フランス象徴派の詩を日本に初めて紹介し、詩壇に大きな影響を与えた。本作以降、大正2(1913)年刊行の永井荷風の『珊瑚集』【338-148】から同14(1925)年刊行の堀口大学(1892-1981)の『月下の一群』【531-30】までの一連の訳詩集は、日本における近代詩の形成に決定的な役割を果たした。「秋の日の/ヴィオロンの/ためいきの/身にしみて/ひたぶるに/うら悲し」で始まる、ポール・ヴェルレーヌ(1844-1896)の「Chanson d'automne(秋の歌)」の翻訳「落葉」は、名訳として特に名高い。