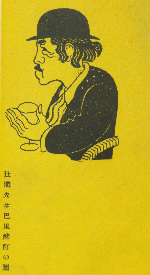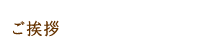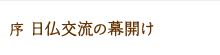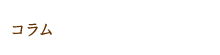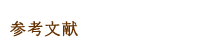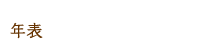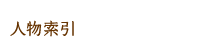![]()
第1章 文学
1. 文学者の見たフランス
「ふらんすへ行きたしと思へども/ふらんすはあまりに遠し/せめては新しき背広をきて/きままなる旅にいでてみん」(「旅上」)と萩原朔太郎(1886-1942)が歌ったフランスへの思いは、文化人の抱いたフランスへの憧憬を物語る。明治40(1907)年に渡仏した永井荷風(1879-1959)や大正2(1913)年5月に渡仏した島崎藤村(1872-1943)らに影響され、とりわけ第一次世界大戦後には多くの小説家や画家、新聞記者らがフランスへと旅立った。当初の憧憬に満ちた彼らの眼差しは、やがてフランスのより深い本質へと注がれ、憧れと現実の乖離を目の当たりにしたとき、その受容と拒絶との間で揺れ動いていく。荷風、藤村から横光利一(1898-1947)らへと受け継がれるフランス文化受容の流れは、生きるための極限の生活の中で、冷めた視線でパリの実像を描き出した金子光晴(1895-1975)の自伝的記録『ねむれ巴里』【KH248-72】をもって、ようやく「憧れ」との葛藤から解放されることとなる。
明治時代に渡仏した人々
有島生馬『南欧の日』新潮社,大正5(1916)【F13-A76ウ】
洋画家・小説家の有島生馬(1882-1974)は、明治38(1905)年6月に渡欧し、主にイタリア、フランスで絵画や彫刻を学んだ。後に来欧した兄の武郎(1878-1923)とともに欧州各地を遍歴した後、パリにとどまり同43(1910)年2月に帰国した。帰国後は、画家ポール・セザンヌ(1839-1906)の紹介や二科会の創設などのほか、文壇でも活発な活動を行った。本書は、南欧の風物を背景にした短編集であり、収録作品の中で唯一フランスが舞台となっている小説「テムプル夫人」では、パリに滞在する日本人画家を主人公に、展覧会で出会った謎めいた貴婦人との交際の顛末が描かれている。
永井荷風『新編ふらんす物語』 博文館,大正4(1915)【F13-N14-13ウ】
4年間の米国滞在の後、明治40(1907)年に横浜正金銀行リヨン支店員として渡仏した永井荷風は、8か月間のリヨン勤務と退職後2か月間のパリ滞在を経て、翌年7月に帰国した。短期間の滞在にもかかわらず、フランスでの体験が荷風に与えた影響は大きく、その作品は日本の文学におけるフランスへの憧憬の端緒となった。
本書は、帰国後に種々の雑誌に投稿した作品と書き下ろし作品を収録した、初版『ふらんす物語』が発禁処分となった後、出版社の要請により、荷風の意思に反する形で構成を変更し出版されたものである。大正8(1918)年以後の版では、当初『あめりか物語』【17-330】末尾に収録された「船と車」、「ローン河のほとり」、「秋のちまた」の3編を冒頭に置き、全体を再構成した形が踏襲されているが、岩波書店の『荷風全集』【KH385-E6】第5巻では初版の構成で読むことができる。
与謝野寛・与謝野晶子『巴里より』金尾文淵堂,大正3(1914)【349-294】
明治45(1912)年5月、与謝野晶子(1878-1942)は、前年渡仏していた夫の寛(鉄幹、1873-1935)を追ってシベリア鉄道で渡欧した。本書は、写真をふんだんに用いた豪華本で、ベル・エポックのフランスを両者の視線で綴った紀行文集である。母国を比較対象とする視点を保ち事実を淡々と叙述する寛に対し、晶子は人間観察に徹する。とりわけ、流行を追いながらも個の表現を忘れず活動的に生きるパリの女性の姿は、晶子に深い感銘をもたらした(「巴里の旅窓より」)。また、2人にとって忘れられない出来事となった、当時72歳の彫刻家オーギュスト・ロダン(1840-1917)との出会いも綴られている(「ロダン翁」)。パリ滞在を楽しみながらも、東京に残した子どもたちへの思いが募った晶子は同年10月に、寛も翌年1月に帰国している。挿絵は夫妻と親交のあった画家・徳永柳洲(1871-1936)によるものである。
大正時代に渡仏した人々
石川三四郎『一自由人の放浪記』平凡社,昭和4(1929)【595-77】
無政府主義の作家・石川三四郎(1876-1956)は、大逆事件後の政府の圧迫を逃れて、大正2(1913)年3月にフランス船で渡仏し、ヨーロッパ各地を転々とする生活を送った。フランスには最も長く滞在し、同9(1920)年10月に帰国している。本書は、主にヨーロッパ滞在中に執筆され、新聞や雑誌に発表された文章を収録した随筆集であり、西欧文明に対する鋭い視線やそれを踏まえた日本への考察も随所に語られている。折しも滞欧中に勃発した第一次世界大戦下における体験を綴った文章の数々は、当時の様子を物語る興味深い記録となっている。
島崎藤村『平和の巴里』左久良書房, 大正4(1915)【71-483】
大正2(1913)年5月に渡仏し、パリに居を構えた島崎藤村が、同年8月から翌年5月に東京朝日新聞に寄せたパリ通信をまとめた作品で、第一次世界大戦の勃発にともない、地方都市リモージュへ疎開するまでの出来事を綴っている。この渡仏は後に『新生』【377-133】で語られる事件(姪こま子との恋愛)の重荷からの逃避行でもあった。当初は表面的な印象や出来事が多く語られるが、「大きな設計と意匠とが全体として働いて居る」(「再び巴里の旅窓にて 4」)パリの姿を理解したことで、文明における伝統と創作の関係というフランスのより深い部分へと切り込んでいく変化が見られる。一方で、工芸芸術や他文化を模倣する柔軟性などの日本人の特性にも触れ、日本人として自己を正しく判断し評価する力の必要性も説いている(「音楽会の夜、其他 2」)。
島崎藤村『エトランゼエ』春陽堂,大正11(1922)【915.6-SH45ウ】
大正3(1914)年11月、疎開先のリモージュからパリへ戻った藤村は、同5(1916)年7月に熱田丸で帰国した。本書は、同タイトルで同9(1920)年9月から翌年1月まで東京朝日新聞に、以後は「仏蘭西紀行」と改題し、同10(1921)年4月号から翌年4月号まで『新小説』【雑8-30】に連載した文章をまとめた作品である。帰国当時の「まだ半ば旅にある」(「序」)心の状態から4年を経て語られ始めるパリ滞在の記録であり、旅の途中で出会った日本人たちとの交流も多く描かれている。また、戦争の機運高まるパリの様子や、リモージュの自然に親しんだ生活など、藤村の心情に少なからぬ影響を及ぼした出来事の記述も興味深い。
吉江喬松『仏蘭西文芸印象記』新潮社,大正12(1923)【950.4-Y87aウ】
詩人・仏文学者の吉江喬松(1880-1940)は、大正5(1916)年に第一次世界大戦下のパリへ渡りソルボンヌ大学で学んだ。同9(1920)年の帰国後は、早稲田大学に仏文科を創設して教授を務め、詩人・仏文学者の西條八十(1892-1970)ら後進を育てる傍ら、フランス文学の紹介や翻訳においても功績を残した。本書では、ポール・クローデル(1868-1955)、アナトール・フランス(1844-1924)等の作家についての考察や、新史劇、民衆劇などの動向が語られている。また、フランス文学の名句とともに描き出される、自然や風物と人間との関わりについての叙述も印象深い。
武林無想庵『飢渇信』新時代社,昭和5(1930)【595-236
】
武林無想庵(1880-1962)は、大正9(1920)年の結婚後に妻・文子(1888-1966)と渡仏し、長女イヴォンヌ(五百子、1920-1965)の誕生後、同11(1922)年に帰国する。翌年に再度渡仏するも生活に行き詰まり、文子が飲食店の経営や日本舞踏家としての活動で生活を支えた。元来奔放な性格の文子が日本人実業家と同棲を始めた後も、文子に養われる生活を続け、昭和9(1934)年に帰国している。本書は、パリ滞在中に日本の雑誌に寄稿したパリ生活の報告をまとめて刊行された作品であり、自身の恋愛遍歴や人間関係を、私小説やエッセー、告白などを織り混ぜた自由な文体で綴っている。
昭和前期に渡仏した人々
辻潤『絶望の書』万里閣書房,昭和5(1930)【603-222】
昭和3(1928)年1月、評論家・辻潤(1884-1944)は、読売新聞社第1回パリ文芸特置員の肩書で、婦人運動家・伊藤野枝(1895-1923)との間に生まれた長男・一(まこと、1913-1975)を伴い渡仏し、翌年1月にシベリア経由で帰国した。本書収載の「巴里の下駄」は、読売新聞に寄せた通信をまとめたものである。ダダイストを称する辻は、放浪生活を送りながら独自の視点による文明批評を世に出した。本書では、名所見物には興味を示さず持参した小説『大菩薩峠』に読み耽る様子や、西洋文明を取り入れたことにより日本固有の文化が失われたことへの憂いも綴られ、西洋という異なる文明の中で自己を再認識する辻の姿が浮かび上がる。
岡本かの子『世界に摘む花』 実業之日本社, 昭11(1936)【700-71】
岡本かの子(1889-1939)が人気漫画家である夫・一平(1886-1948)、息子・太郎(1911-1996)、同居の青年ら5人の一行で渡仏したのは、昭和4(1929)年暮れのことであった。一平の印税により経済的に余裕のあった一家は、セーヌ川の両岸にそれぞれ家を持ち、かの子自身もオペラや有名レストランに足を運び、当代の画家の個展を楽しむなど、自由で開放的な空気を存分に味わった。同7(1932)年に夫妻は帰国したが、太郎はパリに残りソルボンヌ大学で哲学や民族学などを学ぶ一方、抽象芸術運動や超現実主義に接近し多くの芸術家と交流を持った。本書は、帰国後に小説家に転身したかの子が著した物語的紀行文集で、中扉の題字や挿絵もすべてかの子自身によるものである。「仏蘭西篇」の扉に描かれているのは、ロンシャン競馬場に来た男女の様子である。
林芙美子『私の紀行』新潮社, 昭14(1939)【780-237】
林芙美子(1903-1951)は、昭和6(1931)年11月にシベリア鉄道経由で渡仏した。自伝的小説である『放浪記』【596-254】が人気を博した芙美子にとって、小説家としての新境地を模索する旅であった。本書では、三等列車を乗り継ぎながらの一人旅の様子も描かれ、パリまでの旅程に要した費用が詳細に記録されている(「巴里まで晴天」)。世界恐慌下のパリでは円が暴落し苦しい生活を余儀なくされたが、庶民的な街でカフェやパン屋に通い、画廊や映画館、時に歓楽街にも足を運ぶなど、パリの空気を存分に味わい自らの感覚を磨いていく芙美子の姿がうかがえる。約半年の滞在を終えて翌7(1932)年6月に帰国した芙美子は、以後、旺盛な執筆活動に身を投じることとなる。
横光利一『欧洲紀行』創元社,昭12(1937)【729-121】
昭和11(1936)年2月、横光利一は東京日日新聞等の特派員として、ベルリン・オリンピックの取材を兼ねたヨーロッパの旅に出発した。本書は、同年8月の帰国後、旅行中の日記と書簡を元に再構成した作品である。自らの積極的な意志ではなく周囲に推される形で渡欧した横光は、到着当初その印象を「巴里の憂鬱」、「身が粉な粉なに砕けたやう」といった感覚表現を多く用いて語っているが、次第に客観的な視点へと転じ、ファシズムの台頭で政治的混乱の渦中にあるパリの情勢を描写していく。一方で、アンリ・マティス(1869-1954)やポール・セザンヌ(1839-1906)の展覧会にも足を運び、セザンヌの絵画の変化を文学になぞらえるなど芸術に親しんだ様子がうかがえる。本書は、フランス体験を元に書かれた晩年の大作『旅愁』とともに、相容れない異質の文化に身を置いたがゆえの葛藤を描いた作品でもある。
小松清『沈黙の戦士』改造社,昭15(1940)【915.6-Ko61ウ】
大正10(1921)年に初めてフランスに渡った小松清(1900-1962)は、昭和6(1931)年に帰国後、滞仏中に知遇を得たアンドレ・マルロー(1901-1976)らのフランス文学の動向を日本に紹介した。同12(1937)年、報知新聞社欧州特派員の肩書で妻とともに再渡仏した小松は、特派員を退職後、パリに残って雑誌への寄稿や日仏文化交流誌『フランス・ジャポン』【Z51-B510】の編集に携わった。本書は、第二次世界大戦開戦直前の1939年8月末から開戦、ドイツの進軍を経て、1940年6月に陥落直前のパリから脱出し、引き上げ船榛名丸の待つリスボンに向かうまでの記録である。開戦前後の人々の不安、戦地の遠さによる緊張の緩み、ドイツ進軍による緊迫と高まる人々の恐怖の様子を、フランスへの愛惜を交えて叙述した、記録文学としても価値の高い作品である。
岡田八千代『白蘭』大元社,昭和18(1943)【914.6-O388ウ】
岡田八千代(1883-1962)は、演出家・劇作家の小山内薫(1881-1928)の実妹で、フランスで名を成した洋画家・藤田嗣治(1886-1968)の従姉でもある。小説家・劇評家として知られた八千代は、夫の画家・岡田三郎助(1869-1939)とともに昭和5(1930)年に渡仏した。夫婦仲の悪化により夫の帰国後もパリに残り、同9(1934)年10月に帰国している。パリ滞在中に執筆したエッセーを多く収録した本書では、街の眺めや菓子、季節の花など女性ならではの題材が、豊かな色彩表現を用いて鮮やかに描き出されている。